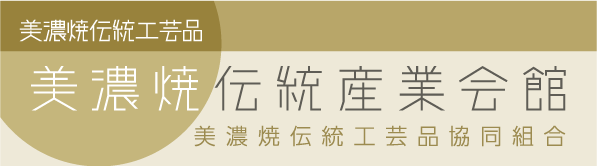やきものワールド
やきものワールド
日 時 2025年2月28日(金)〜3月4日(火)
会 場 ポートメッセなごや
時 間 10:00-17:00 (最終日のみ16:00終了)
■ろくろ体験 2/28~3/2 3日間のみ
美濃焼伝統工芸士がろくろの製作体験指導をして自分だけのオリジナルな茶碗サイズ食器を製作する。
- 【料金】2,500円
- 【定員】2名
- 【所要時間】30分
- 【対象年齢】小学生以下は保護者同伴
詳細はこちらから、やきものワールド公式サイト (yakimonoworld.jp)
2026美濃焼伝統工芸品・新作品展
第34回春の美濃焼伝統工芸品まつり (終了しました)
会 期 : 令和5年5月3日(水/祝)〜5月5日(金/祝)
場 所 : 美濃焼伝統産業会館
時 間 : 午前9時~午後4時半 ※最終日は午後4時迄
詳細はこちらからどうぞ ↓



土岐市制70周年記念事業 土岐の無形文化財 十五人の陶工
会期:令和7年2月1日(土)から5月11日(日)まで
時間:午前9時から午後4時30分まで(入館は午後4時まで)
場所:土岐市美濃焼伝統産業会館
入館:無料
美濃焼1400年の中で育まれてきた様々な伝統技法を受け継ぎ、発展させて独自の作風にまで昇華させた優れた陶工たちは、国・県・市の無形文化財に指定され、その技術と功績を顕彰されてきました。
本展では、土岐市制70周年を記念して、土岐市が誇る15人の無形文化財保持者の作品を展示し、これからも受け継がれていくであろう陶芸の伝統と技術を紹介します。
添付ファイルはこちらからご確認ください。
https://plus.sugumail.com/usr/toki/doc/790960
美濃焼伝統工芸士 〜茶の湯 水指展〜
~ 伝統工芸士とは ~
伝統的工芸品は、主要工程が手づくりであり、高度の伝統的技法によるものであるため、その習得には長い年月が必要となります。また、生活様式の変化に伴い、伝統的工芸品の需要が低迷していることなどにより後継者の確保育成が難しく、業界全体の大きな課題となっています。この課題に対処するため、(一財)伝産協会では「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」第24条第8号の規定により本事業を実施し、試験に合格した方に「伝統工芸士」の称号を贈り、その社会的地位を高めることにより、伝統的工芸品産業の振興を図っています。
伝統工芸士は、高度な技術を保持する自負と責任を持って産地のリーダーとして産地組合活動への協力、産地振興のための活動を行うこと、また、産地伝統工芸士会に参加または同会を結成し、日本伝統工芸士会に加入して、全国の伝統工芸士相互の交流や活動を通じて産地振興に努めることが「伝統工芸士認定事業実施要領」及び「伝統工芸士認定事業実施細則」に定められています。また、産地の後継者に自身の技術・技法を指導することも伝統工芸士に求められる大きな役割です。
卒寿記念 美濃焼伝統工芸士 真山窯 親子作陶展
会期 令和7年4月1日(火)~5月11日(日)
場所 美濃焼伝統産業会館・特別展示室
卒寿を迎えた今も現役で作陶活動をしている美濃焼伝統工芸士であった伊藤真司の作品と現役伝統工芸士である伊藤浩一郎との親子共演にて展示会を開催する
第38回美濃焼伝統工芸品まつり 終了しました
土岐市制70周年記念事業・土岐市が育んだ芸術 -大陶都誕生からのあゆみ-
土岐市制70周年記念事業 「土岐市が育んだ芸術」 -大陶都誕生のあゆみ-
昭和30年(1955)に始まった土岐市としてのあゆみは、本年で70年を迎えました。
8ヶ町村が合併したことで誕生した本市は、各町村の美濃焼の生産力が合わさり「大陶都誕生」と沸き立ちました。美濃焼産地としての勢いが加速する一方で、芸術的側面においても陶磁器産地ならではの取り組みをスタートさせます。
昭和61年(1986)に日本現代陶彫展を、平成9年(1997)に日本ユーモア陶彫展を主催し、陶磁を素材とした彫刻の公募展を開催しました。平成元年(1989)には、茶の湯の器「織部焼」が史実に登場した慶長4年(1599)の宗湛日記を由来として2月28日を「土岐市織部の日」に制定。記念行事として織部の心作陶展が始まりました。そして、その流れを汲んで始まった現代茶陶展は、平成7年(1995)から現在まで老若男女・国内外の分け隔てなく、広くその門を開けた公募展として続いています。
陶彫、茶陶という極めて特異な公募展は、さまざまな作り手たちの挑戦の場として、作り手とともに歴史を重ねてきました。
本展では、土岐市制70周年を記念し、やきもののまち土岐市ならではの芸術のあゆみを作りてたちの創作の軌跡とともに振り返ります。
★学芸員による展示解説
・令和7年8月16日(土)午前11時~
・令和7年10月11日(土)午後2時~
http://www.toki-bunka.or.jp/events/event/event-11990-c-c-2-c-2
企画展 伝統工芸陶磁名品展 (第2部)
伝統技法を伝承された方々(物故者)の作品や伝統工芸の技術技法で製作された人間国宝・重文等の作家の作品を一堂に展示する。
主な出展作家
荒川豊蔵・加藤卓男・塚本快示・清水卯一・島岡達三・鈴木 蔵
中島正雄・青山禮三・加藤芳州 他
第39回美濃焼伝統工芸品まつり
岐阜県の伝統工芸品展
会期 令和6年8月16日(金)~8月29日(木)
会場 伝統工芸 青山スクエア (東京都港区青山)
問合せ TEL 03-5785-1301
出展は、「飛騨春慶」「一位一刀彫」「美濃焼」「美濃和紙」「岐阜提灯」「岐阜和傘」の6種類の工芸品。


土岐市陶芸協会展2026
会 期 2026年1月6日(火)〜4月5日(日)
時 間 午前10時~午後5時
場 所 とうしん美濃陶芸美術館
出品作家名 安藤博允・川合正樹・河合竹彦
水野輝幸・清水久伸・曽根芳之
齋木俊秀・加藤勝之・加藤保幸
水野雅之・小栗正男・大野繁保
大嶋久興・佐々木二郎・佐々木晨二
三浦繁久・細川令子・伊藤道夫
平田泰司・青木益枝
松山祐利・中島正雄・加藤 仁
塚本司郎・美和隆治・安藤光一・戸松万典
テーブルウェアフェスティバル〜暮らしを彩る器展〜
テーブルウェアフェスティバル 〜暮らしを彩る器展〜
開催日時 2023年12月5日(火)〜12月11日(月) 10:00~18:00
開催場所 東京ドームシティ プリズムホール
『美濃焼と土岐のものがたり-新博物館の展示を先取り!-』
美濃焼伝統工芸品 鳥獣戯画人物展
土岐市陶芸作家 茶の湯 盌展
土岐市内で作陶活動され、技術を伝承された無形文化財保持者の方や伝統工芸品の技術技法で製作された作家の茶盌を一堂に展示する。
11月は伝統工芸品月間。
KOUGEI EXPO IN OKAYAMA
会期 2023.11.3(金祝)〜5(日)までの3日間
会場 コンベックス岡山 中展示場
時間 10:00〜17:00 (最終日は15:00迄 )
https://kougei-expo.com/okayama/
2月・3月の休館日のお知らせ
- 2月の休館日 2日・9日・12日・16日・24日・25日
- 3月の休館日 2日・9日・16日・21日・23日・30日
新春特別企画 美濃焼伝統工芸 百花繚乱 花の陶磁展
現代に受け継がれる美濃焼伝統工芸の技術技法を用い「百花繚乱」と題して、新春らしく美しい花々を表現した彩りのある作品展を開催します。
新春企画展 美濃焼伝統工芸 花鳥風月展
| 花鳥風月とは・・・ | ||||||||
| 花鳥風月とは、美しい自然の景色のこと。 | ||||||||
| 美しい景色とは、山や川、花や木といった自然以外にも | ||||||||
| 虫や鳥などの動物も自然のものとして捉えた景色を表している。 | ||||||||
| 花鳥風月という言葉は、日本で生まれた言葉であり、その昔 | ||||||||
| 貴族や武家たちが自然の景色を詩歌にして楽しむ遊びで | ||||||||
| あった「花鳥風月」が語源とされている。 | ||||||||
| 花鳥風月という遊びの大まかな意味である「自然の景色を | ||||||||
| 表現して楽しむ遊び」から意味が転じて、 | ||||||||
| 現在の「美しい自然の景色」を表す言葉となった | ||||||||
| 今回の展示会は、現代に受け継がれている美濃焼伝統工芸の | ||||||||
| 技術技法を用いた、新春らしい彩のある花鳥風月を表現した | ||||||||
| 作品展を開催します。 | ||||||||